こんにちは!サウナが大好きな皆さん、今日は日本のサウナの歴史について、楽しく掘り下げてみます!
現代では、サウナは私たちの日常に溶け込み、リラックスや健康管理の大切な一部となっています。
そのルーツは実はとても奥深く、温泉や銭湯という伝統的な入浴文化から始まったんです。
今回は、古代から現代に至るまでの日本の温浴文化の歩み、サウナがどのように発展してきたのか。
さらに第1次、第2次、第3次ブームといった流行の変遷にも触れながら、ご紹介したいと思います。
日本の温浴文化のルーツ ~古代から伝わる癒しの知恵~
古来より日本人は、火山に恵まれた自然環境の中で、温泉や湧き水を活用してきました。
昔の人々は、温泉に浸かることで傷や病気の治療を試み、「心身を清める儀式」として温浴を重んじました。
さらに、仏教の教えの効果もあり、8世紀からは寺院への浴場設置が広まりました。
また、大仏で有名な奈良県東大寺では「大湯屋」と呼ばれる木造の大規模浴場が作られ、利用されていました。
江戸時代になると、大衆浴場が普及していきました。
庶民の日常に銭湯が広まり、共同で入浴することが人々の交流の機会としても大切にされました。
温泉地では神聖な儀式として、また銭湯は地域や家族の絆を深める交流の場として、多くの人々に愛されてきました。
このような伝統が、日本で後の温浴文化全般、ひいてはサウナの基盤を築き上げたのです!
日本におけるサウナの誕生 〜東京温泉とその試み〜
日本で本格的なサウナが誕生したのは、戦後間もない時代にさかのぼります。
「東京温泉」という施設は、日本初の国産サウナのひとつとして知られています。
1951年(昭和26年)の開業当初は、温泉、マッサージ、キャバレー、食堂酒場などを併設した高級な入浴施設として注目を浴びました。
東京温泉のサウナ ― 日本独自の温浴スタイル
東京温泉で導入されたサウナは、フィンランドからの直接的な模倣ではありませんでした。
むしろ日本独自の感性や技術を取り入れたサウナとして誕生しました。
- 初代創業者の熱意
初代社長の許斐氏利さんは、射撃競技で活躍していました。
1956年(昭和31年)のメルボルンオリンピックでフィンランド選手団が保有するサウナを目の当たりにし触発されました。
「日本にもこの温浴文化を!」という思いのもと、東京温泉に国産のサウナを導入しました。
最初は一人用の箱型蒸し風呂として作られ、後に複数で利用できるサウナ室へと改良されました。
当時は温度が80度前後で、ゆったりと体を温めるスタイルでしたが、日本のサウナ文化の出発点として大きな注目を集めました。 - 温度・設備の特徴
当初、日本温泉で採用されたサウナは、スチーム配管により蒸気を回す仕組みでした。
最高温度は約80度程度。
欧米やフィンランドの高温サウナとは異なり、ゆったりとした温もりを感じさせるのが特徴です。
ただ、配管がむき出しだったようで、足元はかなり熱かったようです。
残念ながらこの東京温泉は老朽化により1993年に閉館しています。
日本初のサウナとあって現存していれば足を運ぶ人が立たなかったのではないかなと思います。
「箱型蒸し風呂」は現在も各地で体験できます!
今とは少し異なる日本サウナの原型を体験してみるのはいかがでしょうか!
サウナブームの波 ― 時代とともに深まるサウナの魅力
第一次サウナブーム ― 1964年東京オリンピックが火付け役
1964年「東京オリンピック」の開催が開催されました。
なんとここで、日本におけるサウナブームが一気に押し上げられました。
オリンピック中、選手村や競技会場には、本場フィンランド式サウナが設置されたのです。
「本場フィンランド式サウナの設置」はマスコミに大きく取り上げられ、サウナの魅力が国民に広く伝わりました。
このことに刺激を受け、スポーツ施設やカプセルホテル、銭湯などにサウナが続々と併設されるようになりました。
また、当時の日本は高度経済成長期。
庶民が健康や娯楽にお金をかける余裕が生まれたことも相まって、フィンランド式サウナが一大ブームとなったのです。
第2次サウナブーム ― 1990年代、健康ランドとスーパー銭湯の時代
次に訪れたのは、1990年代の「第二次サウナブーム」
この時代は、日本での健康意識が高まるとともに訪れました。
この時代、健康意識の高まりとともに、スーパー銭湯や健康ランドが全国に次々と誕生しました。
スーパー銭湯や健康ランドは従来の銭湯とは大きく異なりました。
お風呂だけではなく、サウナ、岩盤浴、露天風呂、薬草湯、ジェットバス、電気風呂などが併設されたレジャー施設となりました。
この「+α」の付加価値が利用者の心を掴みました。
健康やダイエット効果が注目される中、各施設でサウナは導入されます。
マッサージ、食事処、休憩スペースといったサービスとともに、利用者に充実した体験を提供する場としてサウナは、確固たる地位を築きました。
経済成長とともに、豊かな生活環境の中でサウナが日常の中に溶け込む結果、健康志向とレジャーの融合が進んだのです。
現在も家族や友人と足を運ぶとすると、スーパー銭湯という方も多いかもしれませんね。
筆者も身近でサウナを楽しむのはスーパー銭湯がほとんどです!
第3次サウナブーム ― SNSとメディアが切り拓く現代サウナ
2019年頃からは「第3次サウナブーム」が到来し、再びサウナが注目を集めています。
今までは「サウナ=おじさんが好き」という印象が強かったですが、若年層や女性にも人気のコンテンツとして普及しています。
1つの理由はインターネットやSNSの普及です。
これにより、若者を含めサウナ好きが情報を容易に共有できる環境が整ったことにあります。
「サウナイキタイ」という全国のサウナ施設の情報が瞬時にわかる施設検索サイトが有名です!
2つ目の理由は多彩で個性的なサウナの登場です。
個室サウナやソロサウナ、貸切サウナ、レディースサウナなど、利用者の様々なニーズに対応!
コロナ禍以降のアウトドアブームと連動して、テントサウナやバレルサウナのようなアウトドアサウナも人気を博しています。
これらが若年層の間でサウナがさらに身近で楽しみやすい存在となっています。
さらに、漫画『サ道』の人気に伴い、実写ドラマ化まで実現!
ドラマ内の「ととのう」という言葉が広まり、サウナの魅力が再認識されるようになりました。
今までの「近くの銭湯でサウナに触れる」から「この施設のサウナに行きたい」と サウナのあり方や楽しみ方が新たな次元へと進化しています。
また、老若男女問わず、ストレス社会におけるデジタルデトックスの場としても注目されているのです!
筆者も「第3次サウナブーム」でサウナに魅了された一人です。
日本全国に個性豊かな魅力的なサウナが広まっています。
ぜひ、お気に入りのサウナを見つけてみてください!
サウナは多様化していますが、どこに行くにも安心できるサウナセットを持ち運ぶのもおすすめです!
現代社会に求められる健康と癒し
150年以上前から日本に存在しているサウナ
第3次ブームの中、日本でこれほどサウナが定着している理由は娯楽だけでなく、現代ストレス社会の中で、心身の健康と癒しになっているからこそです。
- 健康効果の明確化
サウナは、あらゆる研究により、健康効果が科学的に明らかになっています。
身体の血行促進、デトックス、ストレス軽減、さらには美容効果まで、多岐にわたります!
これにより、健康志向の高い現代人にとって、サウナが生活の一部として不可欠な存在となりました。 - 精神的なリフレッシュ
デジタル社会、異常気象や環境汚染、感染症の流行といった現代はストレス社会真っ只中。
残念ながら、日々心身へのストレスは増加するばかり。
サウナは、デジタルデトックスができる事をはじめ、こうしたストレスを和らげてくれます。
理想的な心身状態を保つためのリラクゼーション効果が高いことからも、必然的に支持されるようになりました。
筆者もこのデジタルデトックスができる環境に非常に魅力を感じています。
仕事や日常生活をはじめデジタル機器に囲まれる日々。
「気づいたらスマホを触り続けている」なんてことも多いのではないでしょうか。
強制的にデジタル機器から離れられるかつ、身体をリラックスできる空間は、頭の疲れも癒してくれるのでお勧めです!
無理せず健康的にサウナは入るようにしましょう!
6. まとめ ― 日本のサウナ史は進化し続ける宝物
今回の記事でご紹介したように、日本のサウナ歴史は、古代の温泉・銭湯の伝統から始まり、フィンランド式サウナの導入を契機に様々なブームを迎えながら発展してきました。
- 戦後の「東京温泉」から始まった国産サウナの誕生
- 1964年東京オリンピックで火付け役となった第一次ブーム
- 1990年代の健康ランドやスーパー銭湯による第二次ブーム
- SNSやドラマ、マンガの影響で再び盛り上がった現代の第三次ブーム
これらの経緯は、日本が経済成長、健康志向、文化の交流を通じて、新しい温浴の形を模索し続けた結果だと言えます。
現代のサウナは、ただ体を温めるだけでなく、心身のリセットやセルフケアのための貴重な場所となっています。
老若男女、誰もがその効果を実感できるようになっています。
これからも、日本のサウナ文化は伝統を受け継ぎつつ、革新的なアイディアと技術によって、さらなる発展を続けるでしょう。
皆さんも、その歴史に触れながら、心と体をリフレッシュする素敵な時間を楽しんでください!

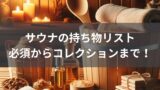

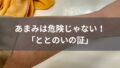

コメント