いまや私たちの日常に欠かせない「サウナ」
その起源は北欧のフィンランドにあります。
古代から受け継がれてきたサウナは、どのようにして現代の形へと進化してきたのでしょうか?
さらに、世界には日本とは異なる多種多様なサウナが存在します。
サウナは単に体を温めるだけでなく、家族や地域の絆を深め、心と体を癒す大切な空間として、古くから発展してきました。
この記事では、フィンランドに限らず、スウェーデン、ドイツ、ロシア、トルコ、メキシコの特徴的なサウナについても詳しくご紹介します。
それぞれの文化や風習を楽しみながら、サウナの奥深い世界を探っていきましょう。
サウナ発祥の地はフィンランド
フィンランドは、現代のサウナ文化の象徴ともいえる国です。
実際、サウナという言葉自体がフィンランド語に由来しており、その歴史は何世紀にも渡ると考えられています!
フィンランドの大地には、原始的な温浴施設が古くから存在していた形跡があり、紀元前から人々の生活に根付いていたとされます。
最も古い証拠としては、狩猟採集社会の中で、体を清めたり、寒い冬を乗り越えるための暖房施設としてサウナが利用されていたという説です。
こうした歴史背景は、フィンランド文化の一部として今日まで受け継がれています。
サウナの起源とされる「ダグアウトサウナ」「アースサウナ」「スモークサウナ」の3種類について、具体的にご紹介します。
サウナの起源:ダグアウトサウナ
ダグアウトサウナは、サウナの起源と言われています。
紀元前の時代から存在していたとされ、狩猟採集生活の中で寒冷な環境から体を守るために生まれたと考えられています!
ダグアウトサウナは、文字通り「地面に掘り下げて作るサウナ」です。
地中に設置されているため、周囲の土が自然の断熱材として働きます。
そのため、外気温の影響が少なく、内部の熱がじんわりと長持ちするのが大きな特徴です。
丸太を燃やし、熱した石に水をかけることで蒸気を発生させて温めていたようです。
ダグアウトサウナからロウリュが既に生まれていたようですね!
サウナの原型:アースサウナ(マーサウナ)
ダグアウトサウナの次に生まれたのが「アースサウナ」です。
アースサウナはサウナの原型ともいわれており、傾斜地を活用して作られました。
このサウナは、まず地面に穴を掘り、その上に小さな小屋を建てるというシンプルな構造。
内部には石製の炉が設置され、薪を燃やして石を温めることで室内の温度を上げます。
また、木製のベンチが備えられており、利用者がリラックスできる空間が提供されました。
さらに、屋根には土をかぶせ、その上に草を生やすことで、自然との一体感を強調するデザインです!
現代サウナの始まり:スモークサウナ
スモークサウナ(Savusauna)は、現在のサウナの始まりとも言われています。
フィンランドで長い歴史を持つ伝統的なサウナの一つです。
スモークサウナは、薪を室内で直接燃やすことで室内を暖める非常にシンプルな方法を用いています。
次の過程を経て入浴ができます。
- 煙突を設けず、薪が燃えて発生した煙が室内に充満させる。
- 一定時間放置してから煙を抜く。
- 清潔な空間が整えられる。
こうして、入浴者は煙の香りが残る心地よい空間でリラックスすることができます。
フィンランドでは、スモークサウナは第二次世界大戦前までは主流!
現在では全体の1%程度にまで減少しています。
準備に手間と時間がかかるため、簡便なサウナが普及する中で少数派となりましたが、それだけに貴重な体験と言えますね。
日本では残念ながらスモークサウナを体験できる施設はかなり少数です。
独特の香りと温もりに包まれながら、古来から続くサウナ文化の深さを感じる。
ぜひ一度は体感してみたいですね!
世界各国の伝統的な蒸し風呂・サウナの魅力
サウナや温浴施設は、各地域で独自の進化を遂げ、文化と深く結びついています。
日本ではサウナ室内にテレビが設置されていることが一般的ですが、世界各地のサウナにはまた違った特徴や魅力が存在します。
スウェーデン、ドイツ、ロシア、トルコ、メキシコのサウナの特徴をご紹介していきます。
聞きなれないサウナ用語も、意味が分かると面白いですよ!
世界のサウナ①:スウェーデン「バストゥ」

スウェーデンでは、サウナは「バストゥ」と呼ばれています。
中世からスウェーデンの農村地域で一般的に利用されていた温浴施設です。
スウェーデンのサウナは日本のアウトドアサウナに近い印象がありますね。
日本ではテントサウナなどで湖や海で水風呂を体感できる施設もあります!
自然との調和で普段と違うサウナ体験をしてみるのもおススメです。
世界のサウナ②:ドイツ「アウフグース」

ドイツにはバラエティ豊かなサウナがあり、サウナのテーマパーク、大自然の中のサウナなど様々です。
その中でも共通されている文化をご紹介!
ドイツサウナはマナーを重んじるかつ、アクティビティとして楽しむという一面を持ち合わせています。
また、裸で混浴という日本では考えられない体験も待っています。
旅の貴重な体験として、一度は経験してみるのもひとつかもしれませんね。
そして、アウフグースは今や世界大会が開催されるほど広まっています。
日本でも予選会を観戦することもできるので、ショー感覚で足を運んでみるのもいいかもしれませんね。
世界のサウナ③:ロシアの「バーニャ」

「バーニャ」という名称は、古代ラテン語の「バネウム」に由来しているとされ、水に浸かる・体を洗う場所という意味が込められています。
呼び方は異なるものの、フィンランドサウナに近しい体験ができそうですね!
世界のサウナ④:トルコ「ハマム」

トルコのハマムは、古代ローマの公衆浴場の伝統を背景に、豪華な温浴施設へと発展。
「ハマム」はアラビア語で「熱い空気」や「お湯を提供する場所」を意味する言葉に由来しているようです。
トルコのサウナは、世界的にも珍しい体験ができそうです!
大理石の床に寝ころんで温まりながら、あかすりやマッサージを受ける。
日本の岩盤浴に近そうですが、温まりながらマッサージを受けられるのは最高ですね!
世界のサウナ⑤:メキシコ「テマスカル」

テマスカルという言葉は、ナワトル語で「熱い石の家」を意味しています。
この言葉は、メキシコの先住民であるナワ族の言語に由来しており、古代から続く蒸気浴の伝統を表現!
単純な入浴というわけではなく、儀式的な意味合いが強いメキシコの「テマスカル」
伝統を感じられる貴重体験になること間違いなしです。
世界のサウナを体感してみよう
サウナの発祥地であるフィンランドを起点に、各国が独自に進化させた多彩なサウナ文化を紹介してきました。
日本では体験できない特徴を持つ、世界中のさまざまなサウナにはその魅力や深い歴史が隠れていますね。
海外旅行の際には、観光だけでなく、各国のサウナ文化を体験することで、心身ともにリフレッシュする特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
各地で違ったサウナ体験を楽しむことで、旅の思い出が一層深まることでしょう。
是非、次回の旅の参考にしてみてください!



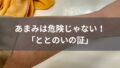
コメント